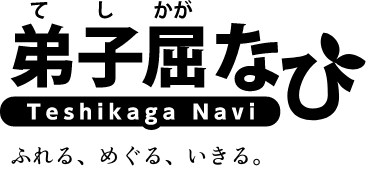2018.01.01
歴史写真館NO.25 高浜虚子~17文字の表現者
 |
昭和8年8月21日、摩周湖を見るために弟子屈を訪れ、鐺別温泉の青木旅館に投宿。翌朝、鐺別川原を散策中詠んだ句が「澤水の川となり行く蕗の中」、虚子59歳の夏でした。明治時代、俳句・短歌の革新と写生文の提唱など、文芸の近代化に心血を注いだ先駆者こそ、虚子と同郷(愛媛県松山市)の先輩、正岡子規でした。庶民化とともに混乱と低俗化に陥っていた俳句に「ものをじっと見、見たものをありのままに書く」という俳句写生論を展開します。その子規の主宰した「ホトトギス」を子規亡き後引き継ぎ 30年あまり、「俳句の神様」として人口に膾炙(かいしゃ)されていました。
7歳上の子規は、21歳にして最初の喀血をし、30歳にして東京根岸の「子規庵」でほとんど病床を離れ得ない人となります。それ以前の子規は、アメリカから輸入されたばかりの野球に熱中したり、精力的に旅に出たりしていましたが、余命との競争になった青年期は、文学で世に出ることを一途に目指します。結婚や恋に道草を食う余裕は子規にはありません。ただ、一度だけ例外的に女性に心 を動かしたことがあります。28歳の時、静養先の松山から東京への帰路に立ち寄った奈良の旅館で、カキをむいてくれた16、7歳の少女を「梅の精」と思って見ほれたことがありました。その時の歓喜を詠んだ句が『柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺』です。
脊椎(せきつい)カリエスの痛みにのたうち回った子規が、最晩年の明治35年5月5日から書き始めた「病牀(びょうしょう)六尺」には、「誰かこの書を助けてくれるものはあるまいか。誰かこの苦を助けてくれるものはあるまいか」と繰り返し訴えています。9月18日、紙を板に張り付け、あおむけのまま「糸瓜(へちま)咲いて痰(たん)のつまりし仏かな」「痰一斗糸瓜の水も間に合はず』。9月19日未明、前日に見舞いに来ていた虚子は、子規の妹・律に起こされた時、夜半過ぎまで聞こえていた子規の「うーん、うーん」といううめき声が聞こえないのに気付きます。正岡子規、本名・升、35年の生涯です。
昭和34年4月1回、85歳の虚子は甚だ健康で、来客に会い、句会を催すのにいささかの疲れも見せていません。午後8時に就寝。その2時間後、突然脳溢血に襲われ、1週間後の4月8日、長い生涯を閉じます。泰然自若たる生涯を過ごした「俳句の神様」の泰然自若たる死でした。辞世の句ではありませんが、虚子はその死生観を『虚子一人銀河とともに西へ行く」と表現しています。虚子もまた宮沢賢治同様、宇宙の音を聞き分けられる耳を持った人でした。
桜ヶ丘森林公園の句碑は、昭和29年に虚子が文化勲章を受章したのを機会に、かつての青木旅館番頭として虚子に直接接し、直筆の色紙をちょうだいした渡辺隆一氏が昭和30年に建立したものです。この句碑によって今日、私たちは望むなら59歳の虚子に向き合い、虚子を通して子規とも出会えます。さらに、昭和初期の鐺別の様子をありありと窺(うかが)い知ることができます。17文字、たった17文字ですが。
てしかが郷土研究会(加藤)